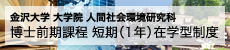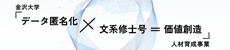社会経済学コース
概要
現代世界は,地球規模で地域統合による収斂化と,統合地域の分極化という相反する流れが進行しています。それは一方で,社会経済の発展を促進すると同時に,他方では,それによって,地域社会においても国際社会においても,コンフリクトや格差 問題,環境問題など,さまざまな問題が発生しています。社会経済学コースは,経済学,経営学の理論を用いながら現代世界の動向を分析し,また現代社会が抱える問題の解決にむけて具体的な方策を提示することを目的とします。
各教員の専門分野
| 氏名 | 専門分野 | E-mail(注2) |
|---|---|---|
| 井出 明 | 観光学(特にダークツーリズム)、アートマネジメント、社会情報学 | akiraide@staff. |
| 碇山 洋■ | 財政学、公共政策論 | ikari@staff. |
| 大木 一慶 | マクロ経済学 | k-ohki@staff. |
| 小澤 裕香 | 社会政策、貧困対策、社会的排除 | y-ozawa@staff. |
| 加藤 篤行 | 応用計量経済学、国際経済学、生産性分析、貿易と成長 | akatoecon@staff. |
| 加藤 峰弘 | 金融論、銀行論 | minehir@staff. |
| 金間 大介 | イノベーション論、マーケティング論 | kanama@staff. |
| 川澄 厚志 | 観光まちづくり、地域経営論、コミュニティ開発 | kawasumi@staff. |
| 菊地 直樹 | 環境社会学、自然再生、エコツーリズム、順応的ガバナンス | nkikuchi@staff. |
| 小林 信介 | 経済史、日本史、地域史、社会運動史、移民史、民衆史 | kobashin@staff |
| 齋藤 毅 | 国際経営、国際人的資源管理論 | tsaito@staff. |
| 阪口 博政 | 管理会計(医療分野) | sakaguchi@staff. |
| 佐藤 清和☆ | 財務会計 | kiyosato@staff. |
| 佐藤 秀樹 | 英仏金融史、ヨーロッパ金融 | h-sato@staff. |
| 佐無田 光 | 地域経済学 | samuta@staff. |
| 白石 英巨 | 都市計画・建築計画、土木計画学・交通計画、まちづくり | hideoshiraishi@staff. |
| 鈴木 智気 | 経営管理論 | tosuzuki@staff. |
| 瀬尾 崇 | 政治経済学、経済学史、進化経済学 | t-seo@staff. |
| 髙橋 涼子☆ | 社会学、福祉・医療社会学、障害学、ジェンダー学 | takahasi@staff. |
| 竹島 貞治 | 簿記会計、会計制度、会計理論、会計史 | take470@staff. |
| 田邊 浩 | 社会学 | tanabeh@staff. |
| 千葉 芳広 | 医療史、労働史、農業史、東南アジア史 | hirochiba@staff. |
| 張 婧 | マーケティング論(サービス・マーケティング、 小売マーケティング、顧客理解、価値共創) | j-zhang@staff. |
| 堤 敦朗 | 社会福祉学、公衆衛生学、国際精神保健学 | atsuro@staff. |
| 土井 妙子 | カリキュラム論 | tdoi@ed. |
| 林 直樹 | 農村計画学、生態系サービス、撤退の農村計画 | nhayashi72@staff. |
| 藤澤 美惠子★ | 応用ミクロ経済学(実験経済学・都市経済学等) | fujisawa@staff. |
| 星野 伸明 | 経済統計学 | hoshino@kenroku. |
| 正木 響 | 経済発展論、西アフリカ経済史、貨幣・通貨、世界経済論 | tmasaki@staff. |
| 眞住 優助 | 社会学、国際社会学、移民研究 | ymazumi@staff. |
| 眞鍋 知子 | 社会学、地域社会学 | manabe@staff. |
| 丸谷 耕太 | コミュニティ・デザイン、文化的景観、伝統工芸、 ランドスケープ論 | maruya@staff. |
| 村上 慎司 | 社会保障論、経済哲学 | shinji.murakami@staff. |
| 森山 治☆ | 社会福祉学、医療福祉論、ケア論 | moriyama@ed. |
| 山田 菜緒子 | インタープリテーション、遺産資源保全、持続的な観光、来訪者研究 | yamada@staff. |
| 柳 在圭☆ | 生産システム、経営工学、サプライチェーンマネジメント | yoo@staff. |
| 和田 一哉 | 開発経済学 | kwada@staff. |
注意事項
- ■は令和8(2026)年3月に、☆は令和9(2027)年3月に、★は令和10(2028)年3月に異動予定のため主任指導教員になれません。
- メールアドレスは「E-mail」の欄の後に「kanazawa-u.ac.jp」をつけてください。
研究室紹介

当研究室は「集落(むら)づくり」に関する研究室ですが,最大の特徴は,従来型の「活性化」に関する研究に加え,国全体の人口が減少する時代の「戦略的な集落づくり」「再興の可能性を残した『集落の縮小』」に関する研究を行っていることです。研究全体の基礎にあるのは,農業土木学・農村計画学であり,「生態系サービス」「国レベルの食料確保」についても重視しています。前述の「再興の可能性を残した『集落の縮小』」については,次の4点,すなわち,(1)土地の土木的な可能性(例:耕地の復旧が容易),(2)土地の権利的な可能性(例:再興時の権利的な障壁),(3)集落の歴史的連続性,(4)集落における生活生業技術(昔ながらの自然と共生した生活や生業に必要な技術や知恵,その場所の山野の恵みを持続的に引き出す技術や知恵)を重視しています。また,「戦略的な集落づくり」を考えるための道具として,ボード(カード)ゲームの開発や評価も行っています。当研究室の目標は,理想の集落の形を示すことではありません。わたしたちが大切にしていることは,現実の縮小を直視した上で,「集落の生き残り」の選択肢を増やすことです。
研究課題名/プロジェクトタイトルと研究責任担当者
既存の集落づくりに「再興の可能性を残した『集落の縮小』」という選択肢を組み込む方法(林直樹)
その他の研究テーマ・課題等
- 耕地の粗放的な活用の選択肢
- 集落の歴史的連続性の「可視化」
- 「生活生業技術レッドリスト(レッドデータブック)」の作成と評価
- 「生活生業技術」に関する再現可能な記録手法の開発と評価
- 思考実験の道具としてのボード(カード)ゲームの開発と評価
- 現代型の集落移転
- 都市と農村の一体的な生き残り策